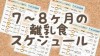1ヶ月健診赤ちゃんとママの健診内容は?持ち物や費用
少しずつ赤ちゃんとの生活に慣れてきた頃、赤ちゃんにとって初めてのお出掛けになることも多い「1ヶ月健診」がやってきます。ママにとっても、初めて赤ちゃんと一緒に外出することはドキドキしますね。
健診は赤ちゃんが順調に育っているかを検査したり、ママの産後の体調回復を確認します。また、ママが産後のトラブルや悩みを抱えている場合は、医師に相談できる良い機会にもなります。1ヶ月健診は任意の健診ではありますが、これから元気に育児をしていくためにも、ママの体調をしっかり診てもらうことも大切です。ぜひ受診しましょう。
ここでは1ヶ月健診でママが慌ててしまったり不安になったりしないよう、気になる赤ちゃんとママの1ヶ月健診の内容、必ず持っていくもの、あると便利なもの、健診の際のポイントについて解説します。
赤ちゃんの健診内容
まずは赤ちゃんの健診について説明します。
赤ちゃんの健診では、「体重の増加」と「先天的な病気の有無」の確認がメインとなります。詳しい健診内容について見ていきましょう。
身体測定
身体測定では、身長・体重・胸囲・頭囲の測定をします。
特に気になるのは身長と体重ですが、この頃の赤ちゃんの成長ペースは個人差があります。平均として、身長は55cm、体重は3,000~5,000gですが、医師から特に何も言われなければ平均と誤差があっても気にしないようにしましょう。
特に身長に関しては正確に測れないことも多く、ママが「成長が遅いのでは…」と心配になることもしばしばありますが、次の健診での成長を楽しみにのんびりと待ちましょう。体重はミルクの飲み具合がどうかを確認します。
問診
問診では、普段の生活について医師が確認してくれます。
母乳やミルクについて、赤ちゃんの飲み具合、睡眠状態、排せつについてなどです。ママも心配事があればこの際にぜひ聞いてみて下さい。医師がアドバイスをくれますよ。
聴診
心臓の音に問題がないかなどをチェックします。
触診
触診では、赤ちゃんの全身を細かくチェックします。
おおよそ下記の項目について医師が診てくれます。
・黄疸の有無
・大泉門の状態(頭部の前面にあるすき間)
・目が見えているか
・首の状態
・口の中の状態
・股関節脱臼の有無
・おへその状態(とれたへその緒のあとが乾いているかどうか)
・腹部や陰部のヘルニアの兆候
・原子反射チェック(刺激を与えた際に反射的な反応を見せるか)
もし何かしら病気があったとしても、この健診で早期発見することにより、早く治療することができます。

- 1ヶ月の赤ちゃんの睡眠時間や授乳間隔の生活リズム
生後1ヶ月の赤ちゃんの睡眠時間について、授乳間隔や回数について、赤ちゃんと一緒に外出してもいいの?という疑問や便秘理由や解消のマッサージを動画で紹介し生後1ヶ月の赤ちゃんが喜ぶおもちゃを紹介します。
ビタミンKシロップの投与
赤ちゃんはビタミンKが不足しがちです。ビタミンKが足りないと、ビタミン欠乏性出血症を起こしやすくなるため、1ヶ月健診で投与してくれます。
ビタミンKとは
緑黄色野菜や海藻類、緑茶、植物油などに多く含まれるビタミンです。
ビタミンKは骨の形成に必要とされていて、赤ちゃんの成長にもとても大切な要素です。
ママの健診内容
次にママの健診について説明します。ママは産後の体調がしっかり回復しているかどうかを確認します。
身長と体重
体重測定は大体行われるようです。他にはママによって妊娠時・出産時から必要と思われる検査が行われます。
診察と問診
診察では子宮の戻り具合や、母乳育児のママであればおっぱいの状態などを確認します。また、悪露の量や状態の確認もします。
また、一般的に産後の入浴は一ヶ月健診を済ませてからの方が無難です。シャワーだけじゃ物足りなく感じてしまうでしょうが、感染予防のためにも1ヶ月健診である程度体の回復を確認してからの入浴が安心ですよ!産後何かしら不安やトラブルを抱えている場合は、問診時に相談しましょう。
尿検査・血液検査
それぞれのママの必要に応じて行います。
必要な持ち物は事前に準備!当日は時間に余裕をもって出発しましょう
次に1ヶ月健診の大まかな流れと、持っていくものについて説明します。
特に持ち物に関しては当日慌てないように、事前に確認してそろえておくに越したことはありません。

1ヶ月健診当日は赤ちゃんにとって初めてのお出掛けにもなるので、途中で赤ちゃんが泣いてしまったり、おむつ替えをしたりなど何かと手間取ることもあるかもしれません。時間には余裕を持って外出しましょう。
健診を受ける場所は出産した産院
1ヶ月健診は、基本的に出産した産院でママと赤ちゃんで一緒に行われますが、場合によっては小児科、産院に別れることもあります。出産した産院で案内があるはずですので確認しましょう。1ケ月健診前に産院から健診の通知が来ていることも多いですよ。
健診時間は赤ちゃんだけであれば約30分程度で終わることがほとんどです。ママも一緒の場合は、お会計までの終了目安として1~2時間程度かかると考えておきましょう。1ヶ月健診は時間の余裕をもって行きましょう。
事前に準備したい必要な持ち物
1ヶ月健診を受けるにあたって必ず必要なものをリストアップしました。
当日忘れ物がないように確認して準備してくださいね。
・母子健康手帳
・赤ちゃんの保険証
・ママの保険証
・乳児健診の無料券・問診票など
・診察券
・乳児医療証(持っている方のみ。市区町村での手続きが必要です)
※乳児医療証とは…乳幼児の医療に関する代金を一定金額保障してもらえるもの。
持っていくと便利なもの
1ヶ月健診は赤ちゃんにとって長時間の外出になります。
赤ちゃんとのお出かけは持ち物も多くなりがちですが、もしもの時のことを考え最低限持っていきたいものは…

・おむつ
・おしりふき
・使用後のおむつを入れるビニール袋
・ミルクセット(ミルクの場合)
・肌着と洋服を1セット
・バスタオル
特に月齢の低い赤ちゃんの場合、着替えが1~2セットあるとミルクや母乳を吐き戻してしまった場合にも安心。バスタオルは健診の際に病院から「持ってきてください」と指示があるかも。
このほかにも、自宅での赤ちゃんのお世話や母乳に関すること、自身の体の調子で気になることなどがあれば、メモに取っておくと健診の際に忘れず医師に質問出来ます。
当日にメモしておきたいことも出てくるかと思いますので、筆記用具を持っていくと尚良いですね!
健診費用は約3,000円~5,000円
1ヶ月健診の費用は実費となりますが、自治体によって補助がある場合もあるので確認しましょう。
また、1ヶ月健診の費用は産院によってその金額が変わります。おおよその金額は事前に知らされるでしょうが、当日は現金を多めに持っていくと良いでしょう。ママと赤ちゃん合わせても通常約3,000~5,000円程度なので、1~2万円程度持ち合わせていれば収まるでしょう。
里帰り出産をしたママは1ヶ月健診まで里帰りをし、その後自宅に帰るケースが多いようです。もし出産した産院で1ヶ月健診ができない場合は、他の病院を探すことになります。
健診は医療費控除の対象になる
医療費控除とは、簡単にいうと「医療費や治療費を年間で多く支払った人に、税金面で優遇する」という制度です。1年間で10万円以上の医療費を支払った場合に適用されます。
(※医療費が年間10万円を超えなかった場合でも、所得金額の5%を超えると申告できる場合があります)

医療費控除の対象となるものについて
1ヶ月健診の費用は健康保険適用外ではありますが、医療費控除の対象となります。その他の医療費とまとめて申告をするので、1ヶ月健診の領収書は大切にとっておきましょう。
また、1ヶ月健診時に公共交通機関を利用した場合、その交通費も医療費控除の対象となる可能性もあるので、詳しくは国税庁のホームページや税務署で確認しましょう。こちらは領収書が発行されない場合がほとんどなので、どの経路でいくら使用したかを念のためメモや手帳などに残しておくと良いでしょう。
妊娠・出産に関係のある費用として医療費控除の対象となるものは以下です。
・妊娠中の定期健診
・出産費用
・助産師による分娩の介助料
・不妊治療費
・人工授精費用
・入院・通院のための交通費
・電車やバスなどでの移動が困難な時のタクシー代
※医療費控除の対象になるかは国の判断になるので使用した状況をご確認ください。
医療費控除の期間はその年の1月~12月が対象
医療費控除はその年の1月から12月までの申告になります。妊娠から出産が年をまたいだ場合は、合算することはできず別々での申告となります。
また、申告は5年間遡って申告をすることができます。5年以内に控除できるものがある場合は諦めずに領収書を探して申告しましょう。
医療費控除を申告する際に必要なもの
医療費控除を申告するにあたって準備するものがあります。
・源泉徴収票
・医療費の領収書
・通院時の交通費を証明するもの(タクシーなどの場合は領収書)
・医療費の明細書(※ネットで簡単に作成ができます。)
・確定申告書A様式(※ネットで簡単に作成ができます。)
申告書は国税庁のホームページで簡単に作成することができ、書類が揃ったら郵送で申告をすることができます。意外と簡単な手続きで済みます。医療費控除を受けると、住民税が安くなるなど優遇が受けられます。忘れずに申告しましょう。
健診は脱ぎ着しやすい服装が便利
1ヶ月健診時は様々な検査があるため、赤ちゃんもママも脱ぎ着しやすい服装がベストです。
また、季節によって温度調節も大切になりますので、特に赤ちゃんの服装は気温に合わせて準備しましょう。

ママの服装
前開きのシャツ+スカートもしくは前開きのワンピースがおすすめです。診察や内診がスムーズなだけでなく、母乳のママは授乳も楽です。
赤ちゃんの服装
基本的には肌着+カバーオールで問題ありません。季節によってポイントがあるので、確認しましょう。
夏の場合
室内では肌着のみでも良いでしょう。
電車内など交通機関では冷房が強くきいています。薄手のカバーオールで防寒しましょう。
冬の場合
ベストやおくるみなどであたたかくしてあげましょう。
交通機関内や病院では暖房がかなりきいています。着こませすぎて暑くならないように注意してください。

- ロンパースとは?いつまで着せる?スムーズな着せ方解説
ロンパースとはどのようなベビー服でいつからいつまで赤ちゃんに着せられるのか、着せ方やオシャレでママに人気のロンパースも紹介。ロンパースとカバーオールの違いや月齢によるサイズの選び方など参考にしてください。
外出時に気を付けたいこと
準備ができたらいよいよ外出です。
病院までの距離やママの状態、同行者の有無などで、ベストな移動手段を選びましょう。

特に同行者がなく、ママが一人で赤ちゃんを連れていく場合は、ママにとって無理や負担がないようにすることが大切です。移動時に抱っこ紐、もしくはベビーカーを使用することがほとんどなので、使い分けのポイントも紹介します。事前に使い方を確認・練習しておくと安心でしょう。
ママのバッグは両手があくようにショルダータイプが便利です。
抱っこ紐
雨の日や階段が多い場所などはベビーカーより抱っこ紐の方が便利でしょう。季節に合わせて注意点を確認し、使い分けましょう。
夏の場合
ただでさえ暑い中、抱っこ紐で密着することにより、ママの体感温度も高くなり、赤ちゃんも相当な熱を感じます。夏場は抱っこ紐を避けるか、涼しい素材の夏用抱っこ紐を使うなど気を付けましょう。
冬の場合
赤ちゃんの頭や手足が無防備になるため、あたたかい上着を着せ、帽子や靴下なども活用しましょう。赤ちゃんが冷えないようにすることが大切です。
新生児から使える抱っこ紐は様々販売されています。
代表的なメーカーは
- ベビービョルン
- ニンナナンナ
- アップリカ
- エルゴベビー
などがあります。
デザインなども様々用意されています。抱っこ紐は赤ちゃんの成長とともに使い続けられる便利なアイテムです。パパが使うこともあるので、ママとパパどちらが使用しても服装に合いやすいデザインや色のものを選ぶママが増えています。ぜひ様々見比べて、お気に入りを見つけましょう。
ベビーカー
夏の場合
抱っこ紐に比べてママの身体への負担が軽く、利用しやすいといえます。
赤ちゃんに直射日光が当たらないよう十分注意しましょう。
冬の場合
冬場は外気に触れて赤ちゃんが寒いことがないよう十分注意し、ブランケットを使うなどして温かくしてあげましょう。雪の日などは、ベビーカーは適しません。抱っこ紐を使いましょう。

- ベビーカーの選び方とA型B型兼用の特徴やおすすめ商品
ベビーカーを選ぶ時に重要なのはママが使いやすい機能を優先することです。赤ちゃんの年齢によりA型やB型やAB型兼用のタイプを選択しましょう。メチャカルなど口コミで人気のおすすめベビーカーと併せて紹介します。
自家用車
自家用車であれば、赤ちゃんが泣くなどしても周りを気にしなくてよいため安心です。授乳やおむつ替えができることも大きなメリットですね。荷物が多くても移動が楽なことも利点でしょう。途中で赤ちゃんのお世話をしなければならない時もあります。その場合は近くのコンビニエンスストアの駐車場に停まるなどし、慌てないようにしましょう。
車から降りた後はベビーカーもしくは抱っこ紐を必ず使用し、赤ちゃんの安全を確保しましょう。
産院に駐車場があるかどうかも事前に確認してくださいね。運転をするのが困難な場合などは、料金は高くつきますがタクシーも便利です。運転手さん以外には誰もいないので、赤ちゃんが泣いてしまった場合などでも慌てずに済みます。
公共交通機関
タクシーなどに比べて料金は安くすみますが、公共交通機関を利用する場合はラッシュ時を避けましょう。様々な人が行きかっているため、感染症のリスクも伴います。
「1ヶ月健診」と「1ヶ月検診」どっちが正しい?
1ヶ月健診とは、「1ヶ月健康診断」もしくは「1ヶ月健康診査」の略称です。「1ヶ月検診」とされる場合もよくありますが、「健診」が正解です。

もちろん、他の乳幼児検診もすべて正しくは「乳幼児健診」。どちらを使用しても大きな問題はありませんし、「検診」と記述してしまう人は多いですが、知ってしまったからには正しい方を使いたいですね!
事前の準備で落ち着いて1ヶ月健診を受診しよう
初めての外出で不安になることも多いかもしれません。ですが、事前にしっかり準備をすれば大丈夫です。赤ちゃんにとって初めての外出なのだと前向きに捉え、落ち着いて行きましょう。
健診後は帰宅したらママも赤ちゃんもゆっくり休みましょう。色々なところに神経も使い、想像以上に疲れているものです。
健診当日、万が一赤ちゃんの体調が悪いようでしたら、無理をせず産院に連絡をし、別日程に変更してもらいましょう。